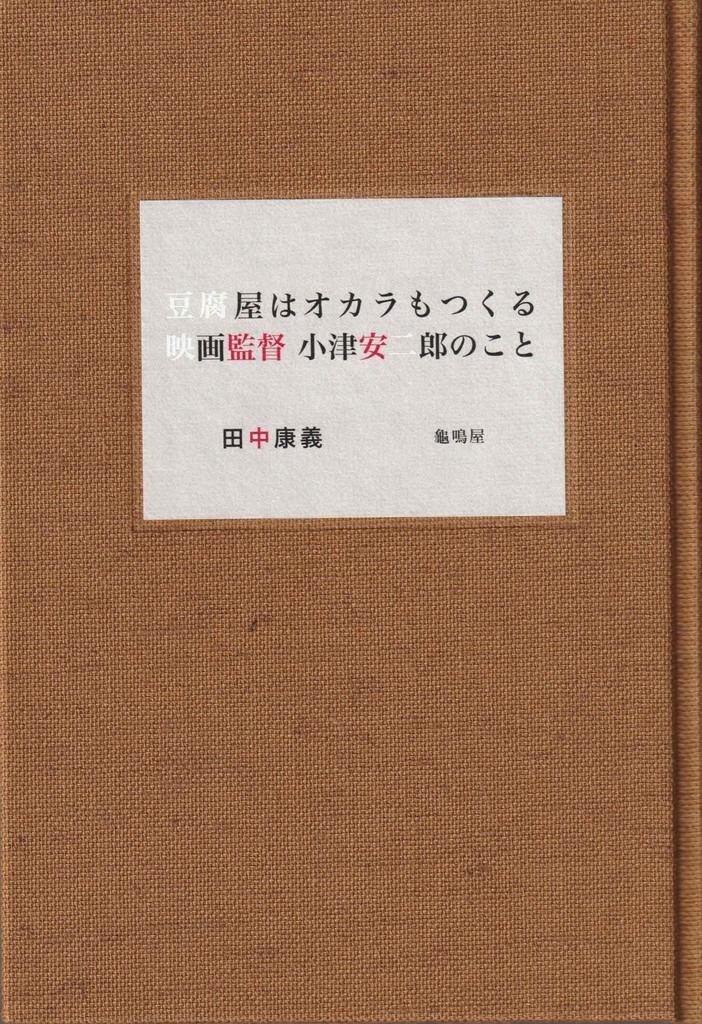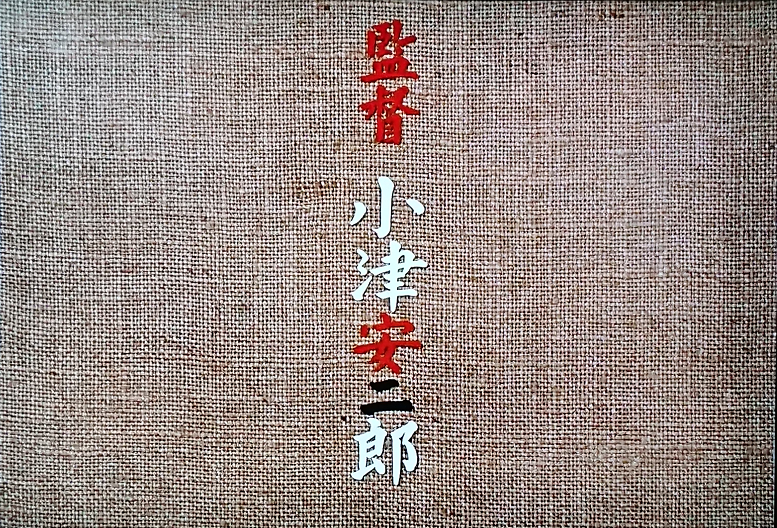アマゾン・プライムビデオでHBO制作のTVドラマ『オリーヴ・キタリッジ』(2015)を見た。エリザベス・トラウトの連作短篇集13篇から4篇をピックアップした全4話のミニシリーズだが、原作の2話ないし3話からエピソードを取って1話にしたものもある。原作は2009年のピュリッツァー賞受賞作で『オリーヴ・キタリッジの生活』(小川高義訳/早川書房)のタイトルで邦訳が出ている。
アメリカ・メイン州の田舎町の薬局に勤めるヘンリー・キタリッジと、中学校の数学教師オリーヴ、この中年夫婦と一人息子の日常生活が、ときに小さな波乱に見舞われながら坦々と描かれる。原作の「訳者あとがき」で、この本は初めから順に、そして最初の一篇だけで判断せずに二篇三篇と続けて読んでほしい、なぜなら「つまみ食いで読んでしまうとオリーヴの強烈な作用(かなり強い毒性もある)を味わいそこなう恐れがある」からだと小川氏は述べている。シャーウッド・アンダーソンの『ワインズバーグ・オハイオ』を引合いに出して、「いくつかの短篇が相互に関連しながら、全体として一冊の長篇のようでもある」というように、ドラマでも全4話(それぞれ約60分ほど)が一篇の長篇劇映画のようだ。ただし、ドラマ版ではオリーヴ・キタリッジの強烈な「強い毒性」は第一話から全開である。
オリーヴを演じるのはフランシス・マクドーマンド。『スリー・ビルボード』の主人公ミルドレッドを髣髴とさせる演技でエミー賞の主演女優賞を受賞している。なにがそんなに気に入らないのとつい聞きたくなるほどいつも不機嫌で、口をひらけば毒をまき散らすオリーヴ。夫のヘンリーが絵に描いたような善人で、誰に対しても愛想がよく面倒見がいいのでオリーヴの偏屈さがよけいに目立ってしまう。ヘンリーを演じるのは『シェイプ・オブ・ウォーター』のリチャード・ジェンキンスで好演。監督はリサ・チョロデンコ。フランシス・マクドーマンドとは『しあわせの法則』(2002)以来の顔合せだ。
原作の小説がいい。田舎町を舞台にした日常生活を描いているので地味といえば地味なのだが、うっかりすると読み過ごしてしまいそうな細部にこの小説の真髄がある。たとえば、ドラマでも第2話になっている「上げ潮」という短篇の最初の方にこういう一文がある。
「パティ・ハウは二つの白いマグにコーヒーをそそいでカウンターに置き、「いらっしゃいませ」と静かに言うと、厨房から出たばかりのコーンマフィンを引き受けに戻った」
パティ・ハウはどうやらダイナー(ファミレスのような食堂)のウェイトレスらしい。
「「おみごと」と料理の係に言う。マフィンの表面がかりっと焼き上がって、あざやかな黄色は昇る太陽のようだ。出来たての匂いで胃のあたりがむかむかする、ということにはならない。この一年で二度そんなことがあったが、そうならないのが悲しかった。ふと気鬱めいたものに見舞われた。三ヵ月は間違ってもだめだよ、と医者に言われている」
それ以上説明しないが、数頁あとでオリーヴ・キタリッジの台詞でこう語られる。
「いい子なんだけど、流産の癖がついちゃって、なんだか寂しげだわねえ」
説明を極力排した抑制した筆致が読者に行間を読むことを強いる。
オリーヴは昔の教え子ケヴィンに偶然出遭う。ケヴィンは子どもの頃、父親と兄といっしょにこの町を出て、いま一人で戻ってきたところだ。オリーヴはケヴィンの車の助手席に乗り込む。ケヴィンは後部座席に毛布に包んだライフルを忍ばせている。ドラマでは助手席に乗り込んだオリーヴが後部座席のライフルをちらと見るカットがある。
「あんたが知ってるかどうか知らないけど、あたしの父親もそうだったのよ」
とオリーヴがいう。心を病んでいたケヴィンの母親は銃で自殺したらしい。
「そう、だった?」「自殺したの」「どういう自殺でした?」「あたしの父? 銃でね」
ケヴィンは死ぬ前に子どもの頃過ごした家を一目見たいと思ってニューヨークから遥々やってきたのだ。
「ひどい巡礼の旅だ……ふたたび来てしまっている……とジョン・ベリマンは書いた。この詩人をもっと早くから知っていたかった」。ケヴィンはベリマン(John Berryman, 1914-1972)の詩を思い浮べる。
「われらをショットガンおよび父親の自殺から救いたまえ」
ベリマンの父親も銃で自殺し、ベリマン自身も投身自殺した。ベリマンを導入して作品を重層的に構築するテクニックが効果的だ。
ドラマでは、ベリマンの詩はバーの壁にピンで留められたナプキンに書かれた文字として登場する。
Save us from shotguns & fathers’ suicides.(Dream Song 235)
オリーヴと同僚の教師で、オリーヴと秘かな恋仲だったジム・オケーシーが書いたものだ。ナプキンに書く場面は第1話に出てくるが、なにを書いたかは明かされなかった。ジムはそのあと自動車事故で亡くなるのだが、あるいは自殺だったのかもしれない。ジム役のピーター・マランがいい味を出している。
回想シーンで、ジムは少年時代のケヴィンにこの町を出て行けと諭す。母親に縛られることはない、と。「クレイジーな女には気をつけろ。心を切り裂かれ恐ろしい目に遭う」と。そしてジョン・ベリマンの詩集をケヴィンに差し出す。ケヴィンは町を出て行くが、ジムの忠告にはしたがわず、病んだ心を抱えて故郷へ帰ってきたのだった。
故郷へ帰ってきたケヴィンはオリーヴと出遭い、崖から海に落ちた女性パティ・ハウを救う。何度も流産したというダイナーのウェイトレスだ。「崖から飛び降りたのか」とケヴィンはパティに尋ねる。「まさか。足を滑らせたのよ」「でも悲しそうだった」「花を摘んでたのよ、元気を出すために」「花なんかでいいの?」「ええ、そんなものよ」。ケヴィンはその答えに胸を衝かれて涙を流す。悲しみに打ちひしがれていても、ほんのささいな喜びに癒されることで生きて行くことができる。それはケヴィンには思いもよらない啓示のようなものだった。
ケヴィンとパティの対話の場面は原作にはない。脚本家のジェーン・アンダーソン(『天才作家の妻 40年目の真実』)が加えたものだろう。もうひとつ、印象に残った原作にはない場面がある。第1話で、オリーヴが居残り生徒の勉強を見ている教室にジム・オケーシーがやってきてオリーヴを廊下に呼び出す。ジムはナイフでリンゴの皮をむきながら詩をつぶやく。ロバート・フロストのThe Road Not Taken(選ばなかった道)だ。字幕ではなく『対訳フロスト詩集』(川本皓嗣編、岩波文庫)から引用しよう。
「黄色に染まった森のなかで、道が二手に分かれていた。
旅人ひとりの身でありながら、両方の道を進むわけには
いかないので、私は長く立ち止まって、
目の届く限り見つめていた――片方の道が向こうで
折れ曲がり、下生えの下に消えていくのを。」
オリーヴは含み笑いをしながら「試験に出す?」と訊く。「いや」というジムの返事に「嫌な人」と返す。ジムはなぜオリーヴを呼び出してフロストの詩を聞かせたのか。オリーヴはそれをどう受け取ったのか。「嫌な人」とはどういう意味なのか。それはわからない。だが、この場面のオリーヴはふだんと違い、少女のようにあどけなく表情にもこわばりがない。それで充分だという気がする。そしてしばらく後に、ジムの運転する車が立ち木に激突する。ジムの死を知ったオリーヴは深夜、夫や息子の目もはばからず号泣する。
エリザベス・トラウトがイーディス・ウォートンの本に寄せた序文が「訳者あとがき」で紹介されている。ウォートンの作品も田舎の寒々しい風景のなかで生きている人々を描いたもので、序文には「『オリーヴ・キタリッジの生活』の勘所というべきものが、ずばり書かれている」と小川氏は書いている。
「こんな昔ながらの田舎の話が、いつまでも滅びない。それは「町や人物をありありと描き出している」からでもあるが、また「人間の魂の孤独をしっかりと見据えて、どこに暮らしていようとも心の中の生活には激動があることを、あらためて感じさせるからなのだ。」」と。
付け加えるなら、シャーウッド・アンダーソンの『ワインズバーグ・オハイオ』の序章「グロテスクなものについての書」もまた『オリーヴ・キタリッジの生活』の勘所にふれているといえるだろう。
「人間が真理の一つを自分のものにし、それを自分の真理と呼び、その真理に従って自分の生涯を生きようとしはじめたとたんに、その人間はグロテスクな姿になり、彼の抱いた真理は虚偽に変る」(橋本福夫訳、新潮文庫)
もしもオリーヴ・キタリッジがグロテスクなまでに常軌を逸した偏屈な人間に見えたとしたら、それは彼女が自らの真理に殉じようとしたためにちがいない。彼女と周囲の人々のいずれが真にグロテスクな人間なのかは問うところでない。
フロストの「選ばなかった道」の最終連は以下のとおり。
「いつの日か、今からずっとずっと先になってから、
私はため息をつきながら、この話をすることだろう。
森の中で道が二手に分かれていて、私は――
私は人通りが少ない方の道を選んだ、そして、
それがあとあと大きな違いを生んだのだと。」
フレデリック・エルムス(『ブルーベルベット』)の撮影は荒涼とした風景をみごとにとらえて美しい。

- 作者: エリザベスストラウト,Elizabeth Strout,小川高義
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2012/10/04
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (10件) を見る